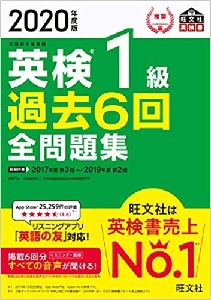二次の面接対策として、「自分の体験・経験を元ネタにしてスピーチを作る」件を別コンテンツで紹介しています。(関連記事をご覧ください)
これを実践するには、まずは「使えそう!」とひらめいた体験をメモするのがキモです。

それだけでもOKなのですが、もう一歩進めて「日ごろからコレを意識しておくとさらに良い」と私が考えているものを紹介します。
「なぜ?問題点はないか?その解決法は?」という意識を持っておく
具体的にはこんな感じです。
子供を見たら「なぜ少子化?解決法は?」と考え、携帯電話をみたら「なぜこれほど広まったのか?弊害はないか?」などと考えるわけです。(対象によってはムリなこともあります)

最後の解決法までちゃんと考えるのはかなり頭に汗をかきますが、それだけでスピーチの概略ができるような気がしませんか?
あくまで私見ですが、この解決法はあまりスケールの大きいものより、身近なものがいいと考えてます。独自性があればなお良しです。
例題を挙げてみます。
例題:温暖化対策 独自性のある身近な解決策を挙げてみると
例えば「温暖化を防止するにはどうするか」という問題なら、
「政治家にCO2排出規制法案を働きかける」
より、
「暖房・冷房を使わないようにする」
「自家用車を使わないようにする」
のほうが良いように思えるのです。

「暖房冷房」「自家用車」はちょっとありふれてる気がするので、
「この冬は湯たんぽ使ってみました。意外と使えるんですよ~」
なんて独自性のある展開になるとさらに良いと思うのですが、どうでしょう?こうした身近な話題のほうが、独自性も具体性も出しやすいものです。
面接官が「ほほう、湯たんぽですか!いつ、どうやって使うのですか?」なんて返してくれて、いかにも話がふくらみそうな気がします。
(ちなみに「湯たんぽ」は英語で hot water bottle というそうです。欧米ではほとんど使われないものなので、説明が必要かもしれません。もし面接で使うのであれば、その説明自体がスピーチの一部として使えますよね)
この例でも、温暖化→湯たんぽ(解決法)というパターンです。
この考え方が良いのは、独自性・具体性という点に加えて
2 会話の展開の予測がつきやすいので準備が可能
3 こうやって考えた一連の流れは、忘れない
といったメリットがあるからです。
特に2は受験する側からすればうれしいところ。
日ごろから物事に対して「なぜなのか・問題点は?その解決法は?」との意識で接していると、スピーチのネタや流れがいつの間にか頭の中に貯まっていきます。
ぜひ実践してみてください。